
イメージ奏法をわかりやすく解説した本が
音楽之友社から出版されました
ワークブック: 『ブルクミュラー 25の練習曲』 表現曲線付
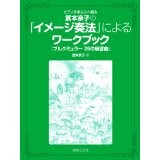
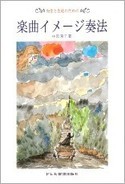
楽曲イメージ奏法とは?
「楽曲イメージ奏法」とは、楽曲を分析して、それを言葉、色、絵、文字等で表現し、把握することにより、楽譜から導き出された“イメージ”を表現できるテクニックや“奏法”を使ったメソッドで、ピアニスト武本京子(中田京子)が自ら演奏会や講座で実践し、教育現場で積み重ねてきたピアノ演奏法、および音楽鑑賞法です。
この奏法は、子供たちへのピアノ指導に対してはもちろんのこと、大人の方にも人生経験が多いほど深い理解が可能となり、より豊かな演奏表現が可能になり、音楽を一層楽しんでいただくことができると思います。
そして、なによりもこの奏法を活用することにより、次の3つの効果が期待できます。
①無意味な音がなくなる。
イメージ奏法では、楽譜に自分のイメージした色を着色していく。その工程の中で、
ただ音を追って練習だけでは見落としがちな、「音」の意味に着目することができます。フレーズの重なりや、隠れた旋律など、立体的に音楽を視覚的に捉え、すべての音に色づけするので、意味づけをしていない音がなくなります。
②全体の構成を把握できる。
イメージ奏法では、楽譜に物語をつけます。作曲家の意図を探りながら、自分が感情移入しやすい情況設定と登場人物を設定して、物語を展開していく。そうすることで、音や小節を追って弾くより全体を把握して演奏することができるのです。
また、色楽譜を広げたときに、演奏上のパワーの配分や心の持っていき方、感情のコントロールが、客観的に大きな位置から捉えることができます。すなわち、全曲を通じて、一番強くメッセージをつたえなければならない所を、自分自身が明確に把握することができるのです。
③自己の確立が可能になる。
音楽を演奏することは、自分自身を表現することです。楽譜の奥底に隠された、人間が言葉でいえない微妙な感情や、魂の爆発や、自然や神への祈り、社会や環境への抗議など、さまざまな想いを感じ、また意見を言える演奏をすることが可能です。
人は、同じものを見聞きしても、感じることや捉え方はさまざまです。同じ自分であっても人は、日々変化します。そのときそのときの自分が、音楽から喚起されたイメージを的確な奏法で音色を使い分ける技術を習得して、心と頭と手と体を一体化させるのが、楽曲イメージ奏法です。
私は、まず自分自身の演奏で実践し、学生とともにこの研究を行っています。
楽曲イメージ研究会メンバーによる研究発表

「楽曲イメージ研究会」では、武本京子の指導のもとに、楽曲を演奏するための、作曲家のことを徹底研究。演奏家は曲ができた背景、作曲的構成、ハーモニーなどから、[楽曲イメージ奏法」で自分がイメージする物語を作成します。
それは、作曲家とイメージや感性を共有するためです。
楽譜にオリギナルイメージストーリを書き込み、色を塗り、どの音にも意味をもたせます。楽譜をしっかり読むことは、自分の内なるものとの対話が必要となります。そして、それを音で表現するために、音色を弾き分けるための、奏法を指導しています。
研究会メンバーは、年二回の発表会を目指して研究発表をしています。わたしは、音楽に自分の心を反映させたり、作曲家から人生を学んだり、音楽の素晴らしさを共に共有するために指導を行っています。
ピアニストを目指す人から、アマチュアで音楽を愛する人まで、言葉で言えない人間の感情や、実際にありえない美しい風景などを想像力という力を借りて楽しんでいます。
http://www55.jimdo.com/app/s41fd9270b463ace4/p8f0abaf5aff0c2a5?cmsEdit=1
 Pianist 武本京子Official website
ロマンティックな時間
Pianist 武本京子Official website
ロマンティックな時間
















